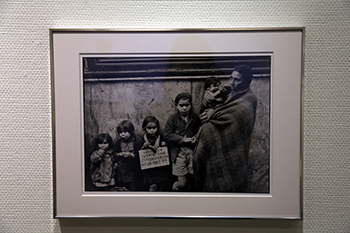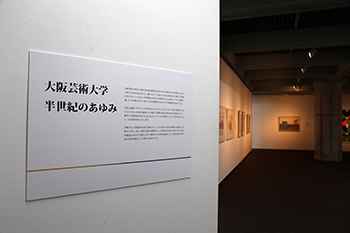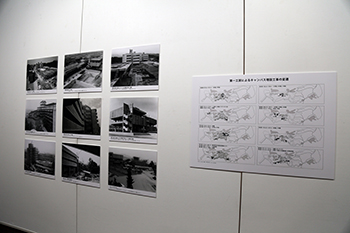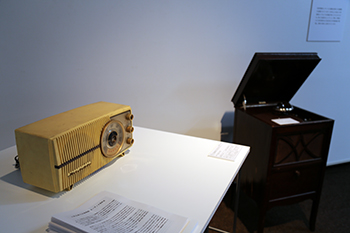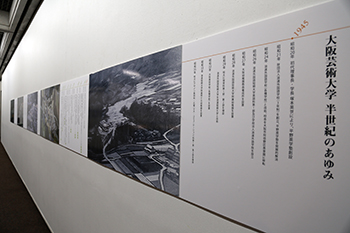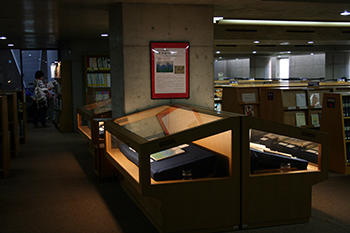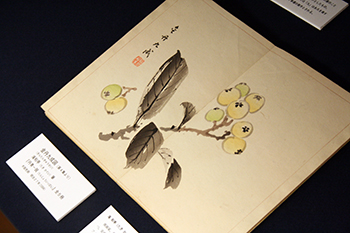先日の雨で、一気に落葉してしまった芸大キャンパス。
1ヶ月前に紹介した9号館前の木も…ご覧の通り。
寒さも到来して、景色も気温もすっかり冬になりました。
昨日の夜は、ちらちらと雪も降りましたね。
さて、今日はキャラクター造形学科の話題です!

先日、学内で「少年サンデー出張編集部」が行われました。
キャラクター造形学科では、漫画家デビューのアシストを趣旨として、これまでにもさまざまな雑誌の漫画編集部の方が来られて学生たちの作品を添削してきました。
今回は、少年漫画誌の中でも特に人気の高い「少年サンデー」の編集部の方が来校!
1959年に創刊し、「この雑誌を読むとまるで日曜日のように楽しい気分に浸れるように」という想いを込めて名付けられたこの雑誌。
少年漫画家を目指す人にとっては、憧れの漫画誌ではないでしょうか?
参加したのは、大阪芸術大学、短期大学部、大阪美術専門学校合わせて16名の学生たち!
完成原稿を手に、編集部の方とマンツーマンでアドバイスを受けます。
絵柄について、構成について、ストーリーについてなどが話され、学生たちの表情は真剣そのもの!!
学生のみなさん、漫画家デビューを目指して頑張ってください!!
そんなキャラクター造形学科では、今週5日(金)まで「Q展」を開催中!
総合体育館ギャラリー一帯を使って、2年生の実習での作品発表が行われています。
漫画コース、アニメーションコース、ゲームコース、そして今年から本格的な実習が始まったフィギュアアーツコースの作品がずらりと展示されています!!
お見逃しなく!!
投稿:島田(OUA-TV)