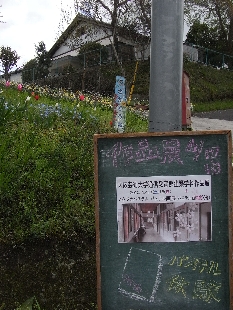|
新学期が始まり2週間が過ぎましたが、春休み中の学生たちの活躍ぶりをお伝えします。 大学内 ガーデンギャラリー その始まりは、2009年9月、ちょうどキャンパス見学会と同じ時期に、体育館ギャラリーの奥にあるガーデンギャラリーで「haramu」展が開催されていました。“haramu=孕む”とは、新しい生命をお腹の中に宿すということ。「haramu」展では、“3人の個性から生まれる新たな表現”ということをテーマに“孕む”という言葉からイメージした作品が展示されていました。その展示を見たときに“haramu=孕む”というユニークなテーマに新鮮な驚きと女性ならではの特質を感じました。 ドーンセンター情報ライブラリー 実際に“子どもを身ごもる=孕む”ということではなく、作品を生み出すことにつながっているわけですが、これは男女共同参画推進センター(旧女性センター)で展示をすれば面白いのではないかと思いました。そして、3人の学生に尋ねたところ、是非やらせてもらいたいということでしたので、大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)情報ライブラリー及び、とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ情報ライブラリーに打診の上、学生たちがそれぞれに企画書を提出し快諾を得て、開催の運びとなりました。 『赤ちゃんモンスター』 中野聡美さん 『you』 『ehka sopo』 久保田美乃里さん 小さいスペースとはいえ、観る側も創り手も意外な感覚に出会える贅沢な空間がしばらくの間、当ライブラリーに存在しました。今回の展示は、とびきり、たくさんの本たちと共存しライブラリーに馴染んでいたように思います。強烈なインパクトで人を惹きつけるのではなく、気づけば自然に作品に近づいているという感じでしょうか。久保田さん、汐見さん、中野さん、素敵な場づくりをして頂き、ありがとうございました。」 『silhouette』 『くるくる』 汐見友里さん とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ情報ライブラリーでは、会場に合わせた新作も作成し、また一味違った展示を行いました。最終日にはギャラリーツアーも行い、情報ライブラリーに来ていた中学生や常連の女性、大学図書館関係者などが参加しました。作品が生まれるに至る学生作家たちの深層心理にまで触れることができ、感動を共有することができました。 すてっぷ情報ライブラリー 4月から汐見友里さんは大阪市内のデザイン会社で、中野聡美さんは地元金沢のデザイン会社で、共に社会人としての一歩を踏み出しました。久保田美乃里さんは4年生となり、いよいよ卒業制作に取り組みます。ギャラリーツアーでの「これからも制作を続けて下さい」「また展覧会をしてください」などの励ましの言葉や今回の展覧会での経験を活かして、きっとそれぞれの道でこれからも頑張ってくれることでしょう。またいつか、より成長した3人でのExihibition3にも期待しています。 |