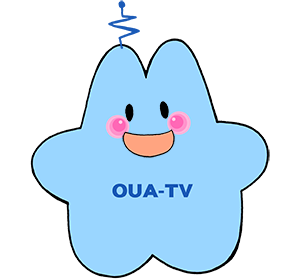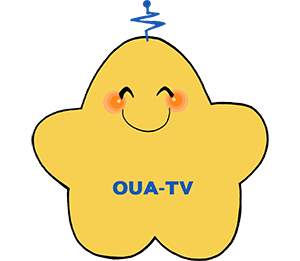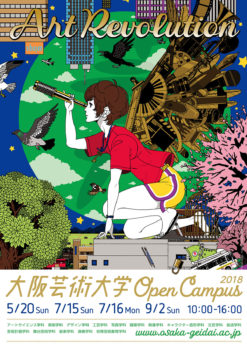毎年さまざまな都市を巡り、本学が総力を結集してお届けする演奏会「大阪芸術大学プロムナードコンサート」♪
今年は、大阪、広島、名古屋の3都市での開催です。
(大阪公演のみ、オーケストラとポップスで別日程、計4回の公演予定。)
今日のブログは、8月21日(月)に行われた大阪公演(オーケストラ)の模様をお届けします!

会場のフェスティバルホールは、2700席ものキャパシティー!
にも関わらず、3階席までびっしりとお客様が入られました。
学生や保護者の方々、大学関係者はもちろん、毎年この演奏会を楽しみにしてくださっているファンの方も多くいらっしゃいます。

指揮は、演奏学科教授の大友直人先生。
演奏は大阪芸術大学管弦楽団が、合唱は大阪芸術大学混声合唱団が担当しました。
そして今年の司会は、放送学科教授の馬場典子先生!
みなさんもご存知かと思いますが、馬場先生は、現在出演中の情報ワイド番組「ゴゴスマ~~Go Go! Smile!~」ほか、これまでニュースからバラエティ・スポーツまで幅広い分野で活躍されてきた人気アナウンサーです。

今回の注目曲の一つ、「青少年のための管弦楽入門」では、放送学科教授でアナウンサーの和沙哲郎先生がステージに登壇。
その場でナレーションを当てて、木管楽器、金管楽器、弦楽器、打楽器それぞれの楽器の魅力へと誘いました。

また、第二部では、教授陣によるソロパフォーマンスも繰り広げられました!
演奏学科教授でピアニストの熊本マリ先生は、G.ガーシュウィン作曲「ラプソディー・イン・ブルー」を演奏♪
ポロンポロンと軽やかなテンポで鳴るピアノの音が、とても印象的な楽曲でした。

プロムナードコンサートでのソロ演奏と言えば、演奏学科教授でヴァイオリニストの川井郁子先生ですよね!
川井先生の演奏目当てでお越しになったという声も、大変多いんです!
今回も、優雅な演奏を披露してくださいました!

そして、今年度より演奏学科准教授に就任された小林沙羅先生も出演されました!
小林先生は、現在の声楽界に欠かせないソプラノ歌手としてご活躍中で、その歌声は繊細で美しく、とても魅力的でした。

さらに、プロムナードコンサートの目玉となっているのが、各都市の地元の高校生とのコラボレーション。

大阪公演では、大阪国際滝井高等学校、大阪府立夕陽丘高等学校、学校法人白頭学院 建国高等学校、学校法人精華学園 精華高等学校の高校生たちと共演しました♪
客席まで緊張感が伝わってきましたが、堂々としたパフォーマンスを見せていただきました!!

さて、大阪公演(オーケストラ)は終わってしまいましたが、まだ他の公演はこれからです!!
若干の残席もありますので、みなさんぜひお越しください!

広島公演(オーケストラ&ポップス)
8月26日(日)広島国際会議場(フェニックスホール)
名古屋公演(オーケストラ&ポップス)
8月28日(火)名古屋国際会議場(センチュリーホール)
大阪公演(ポップス)
9月3日(月)サンケイホールブリーゼ
※台風20号の影響により、順延となりました。
8月23日(木)のチケットをそのままお使いいただけます。
>>チケットの払い戻しなどについては、コチラからご覧ください。
>>プロムナードコンサート詳細はコチラ
投稿:島田(学生課)