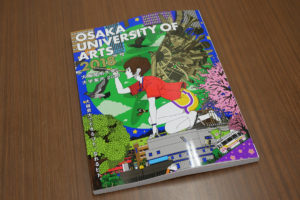今日は、写真学科の授業にお邪魔しました!!
私がお邪魔したのは、1年生を対象にした「写真表現技術実習」という授業。
この授業では、デジタル一眼レフ撮影の基本、スタジオライティングの基本、データ作成からプリントアウトまでのトータルワークフロー、動画撮影の基礎、「Photoshop」などの画像処理ソフトの基礎を学びます。
写真学科の学生の中には、入学時は撮影も編集も初心者という学生もたくさん入学してきます。
これから写真表現を学んでいく1年生にとって、基礎を学ぶために大切な授業なんです!

今回は「Photoshop」を使って写真をプリントアウトするという内容の授業で、写真学科准教授の赤木正和先生と、客員准教授の長谷川裕行先生が指導されていました。
写真のプリントアウトなら、自宅で誰でもできることでは?
と思われた方もいるかも知れませんが、細かい設定を気にしている方は少ないのではないでしょうか。
写真表現において、プリントアウトは大変重要な工程なんです!
写真をプリントアウトする時にやりがちな「フチなし印刷」ですが、写真作品を出力する時には使わないそうです。
何故かと言うと、一つの理由には、フチなしで印刷するとプリンターのヘッドから出るインクが用紙の外にもかかることになり、プリンターの消耗が早くなるから。
もう一つの理由は、フチなしで出した作品を手で触ると指紋がついてしまったり、額やファイルに入れる際に紙の端が傷んでしまうからだそうです。
まず、印刷に適した「解像度」に変える作業を行います。
メニューの「編集」から「画像解像度」を選択すると、幅と高さ、解像度を入力する画面が出てきます。
デジタルカメラで撮影した画像は、「画素」と呼ばれるとても小さな正方形や長方形の画像が集まって表現されています。
画素数が小さいとギザギザした画像になり、大きいと拡大しても滑らかな画像になります。
よくカメラの性能で1600万画素などという言い方がありますが、これは画素が1600万個集まって1枚の写真を表現するという意味。
そして画像のサイズを表すのに「ピクセル」という単位がありますが、これは画素と同じ意味です。
例えば…幅と高さが4000ピクセルの正方形の画像は、4000ピクセル×4000ピクセル=1600万画素の画像になります。
そして解像度とは、画像の密度のことで、単位がdpiなら1インチの中にどれだけ画素が集まっているかを表しています。
今回は、解像度を[300dpi]に設定します。
1年生の授業では、主にA4サイズ(210×297ミリメートル)の用紙にプリントアウトします。
そこで先生がオススメする画像のサイズは、長辺が254ミリメートルになるようにすることだそうです。
254ミリメートルは、ちょうど10インチの長さ。
画像の長辺のピクセル数が解像度のちょうど10倍になるので、作業する時に覚えやすいんですね!
(今回は、300×10インチ=3000ピクセルですね!)
ところで、「解像度は300dpiが適切なのか?」疑問に思ったので、長谷川先生に質問させていただきました。
すると、大体A4サイズくらいまでの紙なら、1メートル以内で見ることが多く、それくらいの距離で作品を見た時に自然に見えるのが300dpiなのだそうです!!
じゃあ、大きくプリントアウトするなら、解像度は高い方がいいのか?…というと、逆なのだそう!
大きいサイズの写真は離れて見ることが想定されるので、200dpiや150dpiで出力されているものが多いらしいです!
そして解像度が高すぎると、今度はプリントアウトすると汚くなってしまうのだそうで、それぞれに適した解像度があると教えていただきました。
解像度を設定したら、プリンターと用紙の種類や部数を選択して、いざプリントアウト!
みなさん、無事に出力できたようです!!
プリントアウトした写真と、モニターに映った画像を見比べて…
「プリントアウトした後のチェックポイントってあるんですか?」と先生に再び質問すると、
「実はモニターとは違う色味に見えるはずです」との返答!
モニターで映っている画像は、太陽光で見た時の色味になっているので、蛍光灯の下で見ると、青っぽく見えるのだそうです。
ですので、プリントアウトした写真は、太陽光と同じ色温度の照明灯で確認したり、昼間なら窓際で見てみるのが一番いいと教えていただきました!!
普段、私も写真をプリントアウトすることがありますが、こんなに色んなポイントがあるだなんて…本当に勉強になりました!!
こういった基礎を身につけて、それぞれの写真表現に臨んでいくんですね。
今回は、写真をアート作品として表現するための出力だそうですが、進級するにつれて広告や書籍などの仕事に繋げるための授業もどんどん展開されるそうです。
写真学科1年生のみなさんの今後が楽しみです★
さて、5月21日(日)開催の大阪芸術大学オープンキャンパス!
写真学科では…!?
 今回のようにパソコンを使ったデジタル画像処理の体験もできます!
今回のようにパソコンを使ったデジタル画像処理の体験もできます!
さらに、芸術情報センター地下2階の実験ドームでは、新たな写真表現として、全天周投影した写真に、音楽学科・演奏学科の学生もコラボレーションして、”音と写真のコラボが生み出す新たなバーチャルリアリティ空間“を表現!!
写真作品展示や4K動画&水中映像上映、スタジオ撮影体験授業など…写真学科の特色が楽しめるプログラムが盛りだくさん♪
ぜひ、お越しください!!
投稿:島田(企画広報部事務室)