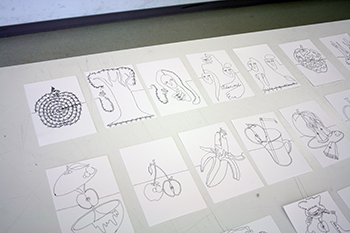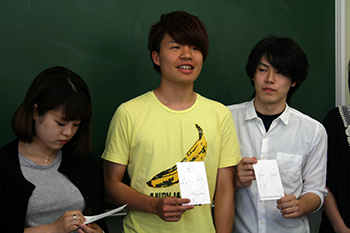今日は、放送学科の授業をご紹介!
放送学科には、【制作】、【アナウンス】、【広告】、そして【声優】の4つのコースがあります。
今回紹介するのは、制作コース2年生の必須科目(他コースは選択必須科目)「制作実習Ⅰ」です。
この授業では、「オーディオ」、「スタジオ」、「中継」、「ドキュメンタリー」、「ドラマ」の5つの制作実習から、前期と後期それぞれで1つずつ選び、実際に番組の制作を行います。
私がお邪魔させて頂いたのは、その中の「ドラマ実習」です!
放送学科教授で演出家・脚本家の長沖渉先生が熱心に指導されていました。

脚本は、放送学科卒業生の山口美佳さんが担当!
写真家を目指す2人の大学生を描いたお話です。
主役の2人は、プロダクションに所属する女優の方が担当されていました。
こうして外部から役者さんが来てくれることで、撮影現場の空気も一気に引き締まりますね!!
今回の撮影では、放送学科に新しく入った撮影用のレールが使われました!
カメラマンの乗った移動車をレール上で走らせながら撮影します。
手持ちや三脚では出せないダイナミックな撮影を行うことができるんですよ。
撮影の途中で何度も長沖先生の指導が入ります。
長沖先生は、NHK連続テレビ小説「ふたりっ子」などを中心に、多くのドラマを手がけて来られた方です。
プロ仕様の機材に触れ、プロの先生を身近に感じながら実習を行うことができるのは、他ではなかなかないことだと思います!

ここで学んだノウハウを、ぜひこれから進む道で役立ててほしいですね!!
投稿:島田(OUA-TV)