こんにちは!ラジオ大阪OBC1314にて毎週木曜日に絶賛放送中の大阪芸大メディアキャンパス-開け!アートの扉-にてアシスタントパーソナリティを務めている加藤万梨子です!
さあ、ついに待ちに待ったクリスマスが今週末に迫ってまいりました!
みなさんは、クリスマスの予定は決まっていますか?もう決まっているという方も、まだ決まっていないという方も、今夜のメディキャンは必聴ですよ!先週もご紹介しましたが、今週末のクリスマスの日に、夢を追う中学生や高校生達の熱い戦いが繰り広げられていることをみなさんはご存知でしょうか?軽音楽の甲子園とも呼ばれている、高校・中学の軽音楽系クラブのコンテスト。その名も『We are Sneaker Ages』!今年で32回目を迎える長い伝統を誇るイベントが行われるんです!
そこで、先週と今週の2週に渡り『We are Sneaker Ages』の本番を直前に控えたこのコンテストに出場される生徒さんの声と演奏曲をどーんと大特集でお届けしています!
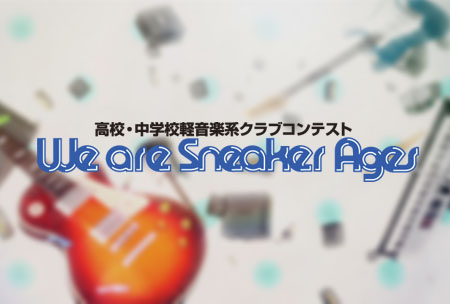 この『We are Sneaker Ages』は、単なるバンドのコンテストではなく、学校の顧問によって指導される部活動が審査の対象になります!それが「甲子園」と呼ばれるゆえんなんですよ!そして、バンドのサウンドだけではなく、ダンスや振り付けなどのステージングやパフォーマンス。さらに応援する観客のマナーや団結力も審査の対象になるのがこのコンテストの大きな特徴なんです!出場者だけではなく、参加するすべての人が主役であるいう『We are Sneaker Ages』にみなさんもぜひ参加してみませんか?
この『We are Sneaker Ages』は、単なるバンドのコンテストではなく、学校の顧問によって指導される部活動が審査の対象になります!それが「甲子園」と呼ばれるゆえんなんですよ!そして、バンドのサウンドだけではなく、ダンスや振り付けなどのステージングやパフォーマンス。さらに応援する観客のマナーや団結力も審査の対象になるのがこのコンテストの大きな特徴なんです!出場者だけではなく、参加するすべての人が主役であるいう『We are Sneaker Ages』にみなさんもぜひ参加してみませんか?
8月の予選からスタートした『We are Sneaker Ages』。今年はなんと134もの学校が名乗りをあげました!そして、12月25日のクリスマスの日に決勝に残った20校によるグランプリ大会を、大阪のベイエリアにある「舞洲アリーナ」にて開催します!
今日の放送では、グランプリ大会に駒を進めた20校のうち、出場順に11組目から20組目の学校を紹介します!
11組目 京都光華高等学校 軽音楽部
12組目 鶴見商業高等学校 軽音楽部
13組目 門真なみはや高等学校 フォークソング部
14組目 交野高等学校 軽音楽部
15組目 阪南大学高等学校 軽音楽部
16組目 西の京高等学校 軽音楽部
17組目 四天王寺中学校 軽音楽部
18組目 同志社香里高等学校 軽音楽部
19組目 奈良県立橿原高等学校 Sound Art Society
20組目 汎愛高等学校 音楽部
今週も、みなさん元気にそして熱く『We are Sneaker Ages』にたいする想いを語ってくれました!『We are Sneaker Ages』を見に行こうと思っているリスナーの方はもちろん必聴ですが、この放送を聴いてから、ぜひことしのクリスマスは『We are Sneaker Ages』でパワーみなぎる生徒さんたちのパフォーマンスをお楽しみください!
さあそして、今日のプレゼント!
「一般入学試験」のスタートを記念し、『大阪芸大オリジナルのクリアファイルケース』を2名様に差し上げます!このクリアファイルは学生さんがデザインしたものなんです!
プレゼントの応募方法は、今日の放送でチェックしてぜひゲットしてくださいね!
さあ、今日の放送もラジオ大阪(OBC1314)にて深夜24時から1時間アート情報満載でお送りします!
































 みなさんこんにちは!映像学科です!
みなさんこんにちは!映像学科です! この前告知させて頂いたACADEMY AWARD「メッセージV」なのですが、学内,学外ともに上映は無事終了致しました!お越しいただいた皆様、メッセージVに伴いご協力していただいた皆様、本当にありがとうございました!
この前告知させて頂いたACADEMY AWARD「メッセージV」なのですが、学内,学外ともに上映は無事終了致しました!お越しいただいた皆様、メッセージVに伴いご協力していただいた皆様、本当にありがとうございました! 3回生はこの制作2で学んだことをバネに卒業制作では、より一層いい作品が作れるよう頑張りますので宜しくお願いします!
3回生はこの制作2で学んだことをバネに卒業制作では、より一層いい作品が作れるよう頑張りますので宜しくお願いします!
 さて、先週からお伝えしている「X’mas Week」。
さて、先週からお伝えしている「X’mas Week」。 と、クリスマスから話がそれてしまいましたが、ここでサンタについてのプチ情報!
と、クリスマスから話がそれてしまいましたが、ここでサンタについてのプチ情報! 今回は数ある発表会の中から「アナウンス実習2」の実習発表会にお邪魔しましたよ♪
今回は数ある発表会の中から「アナウンス実習2」の実習発表会にお邪魔しましたよ♪ 実習発表会では、アナウンスコース担当の先生である小堀先生のクラスと小山先生のクラスが、ニュース番組の再現、ラジオドラマや朗読の上演、生アフレコなど、これまで勉強してきた成果を存分に披露していました!
実習発表会では、アナウンスコース担当の先生である小堀先生のクラスと小山先生のクラスが、ニュース番組の再現、ラジオドラマや朗読の上演、生アフレコなど、これまで勉強してきた成果を存分に披露していました! ニュースでは一体何が起こったのかを正確に、かつ分かりやすく。
ニュースでは一体何が起こったのかを正確に、かつ分かりやすく。 10月8日(土)から10月29日(土)まで、大阪なんばにあるギャラリーCASで、KOSUGI+ANDO「遷移状態」が行なわれていました。この展覧会のキュレーターは室井絵里さん(文芸学科83卒)です。室井さんはインデペンデントキュレーターとして、いままで数々の現代アートの企画を行なってきています。今回はKOSUGI+ANDO「遷移状態」の展覧会をキュレーションしています。キュレーションとは近年特に使われるようになった用語で、企画の立案運営や資金収集まで、展覧会を作ることに大きく関わっている人を指します。また、キュレーターは、自らの視点でアートと社会に切り込み、アーティストと共に展覧会を社会に発信していく仕事でもあります。美術館や博物館の学芸員がそのような役割を果たしていますが、室井さんのように美術館などに属さず、インデペンデントキュレーターとして活躍している人もいます。
10月8日(土)から10月29日(土)まで、大阪なんばにあるギャラリーCASで、KOSUGI+ANDO「遷移状態」が行なわれていました。この展覧会のキュレーターは室井絵里さん(文芸学科83卒)です。室井さんはインデペンデントキュレーターとして、いままで数々の現代アートの企画を行なってきています。今回はKOSUGI+ANDO「遷移状態」の展覧会をキュレーションしています。キュレーションとは近年特に使われるようになった用語で、企画の立案運営や資金収集まで、展覧会を作ることに大きく関わっている人を指します。また、キュレーターは、自らの視点でアートと社会に切り込み、アーティストと共に展覧会を社会に発信していく仕事でもあります。美術館や博物館の学芸員がそのような役割を果たしていますが、室井さんのように美術館などに属さず、インデペンデントキュレーターとして活躍している人もいます。 室井さんは現代美術の批評に関わり、数多くの美術雑誌等に展覧会批評を寄稿してきました。室井さんがKOSUGI+ANDOのキュレーションを行なってきたかを簡単に記述します。1980年代京都アンデパンダン展(京都市美術館)が行なわれており、そこで、KOSUGI+ANDOの作品を体験したそうです。絵画、彫刻、8ミリフイルムなど映像、音響の作品やアクション、パフォーマンス等は一般化していたとしてもインスタレーション形式の作品は日本では珍しかったと思います。京都市美術館一室を使用した林剛+中塚裕子のコラボレーションによるインスタレーション作品に筆者も驚かされました。絵画や版画、彫刻などの批評の現場にいた室井さんは、この目新しいインスタレーション形式の批評とはどのようにあるべきかと考え、それ以来このグループのキュレーションを続けておられるとの事です。
室井さんは現代美術の批評に関わり、数多くの美術雑誌等に展覧会批評を寄稿してきました。室井さんがKOSUGI+ANDOのキュレーションを行なってきたかを簡単に記述します。1980年代京都アンデパンダン展(京都市美術館)が行なわれており、そこで、KOSUGI+ANDOの作品を体験したそうです。絵画、彫刻、8ミリフイルムなど映像、音響の作品やアクション、パフォーマンス等は一般化していたとしてもインスタレーション形式の作品は日本では珍しかったと思います。京都市美術館一室を使用した林剛+中塚裕子のコラボレーションによるインスタレーション作品に筆者も驚かされました。絵画や版画、彫刻などの批評の現場にいた室井さんは、この目新しいインスタレーション形式の批評とはどのようにあるべきかと考え、それ以来このグループのキュレーションを続けておられるとの事です。 写真は、KOSUGI+ANDOさんとのトークと作品です。
写真は、KOSUGI+ANDOさんとのトークと作品です。